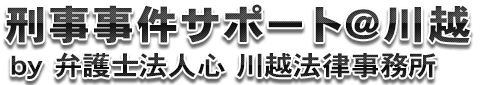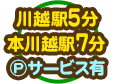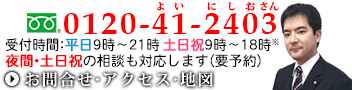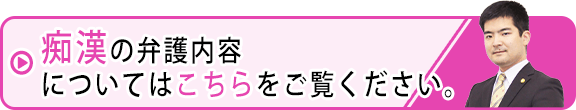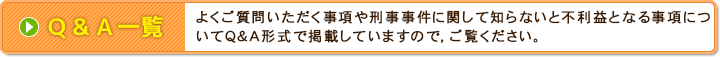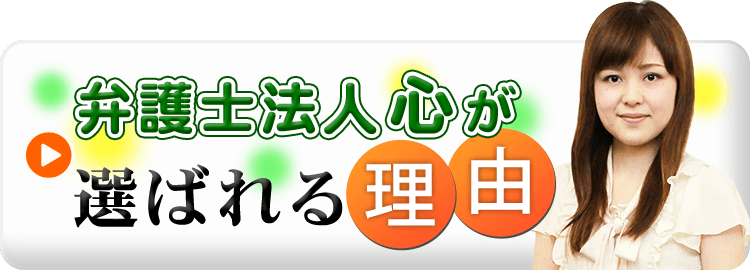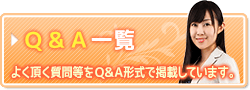「痴漢」に関するお役立ち情報
痴漢事件における弁護活動・弁護士費用の相場
1 痴漢した場合に成立する犯罪
痴漢をすると、各都道府県が定める迷惑防止条例、または不同意わいせつ罪で処罰されます。
⑴ 迷惑防止条例
埼玉県の定める迷惑行為防止条例は以下のように定めています。
“何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 衣服等の上から又は直接人の身体に触れること。
二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(前項に該当するものを除く。)。“
参考リンク:埼玉県警察・埼玉県迷惑行為防止条例の一部改正
公共の場所とは、道路、公園、広場、駅、興行場その他公衆が出入りできる場所、公共の乗物とは、汽車、電車、乗合自動車その他公衆が利用することができる乗物を言います。
そのため、埼玉県において外で行う痴漢行為は、ほぼ全て埼玉県迷惑行為防止条例違反となります。
罰則は、6月以下の拘禁刑(旧:懲役)または50万円以下の罰金です(常習犯は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。
⑵ 不同意わいせつ罪
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。(刑法176条)
わいせつな行為とは、被害者に性的な羞恥心を抱かせる行為をいい、痴漢は不同意わいせつ罪に該当します。
もっとも、電車内での痴漢行為は基本的に、より刑罰の軽い迷惑行為防止条例違反で立件されるケースが多いです。
刑罰の重い不同意わいせつ罪で立件されるのは、女性の下着の中に手を入れる、執拗に痴漢行為を繰り返した等行為が悪質な場合です。
2 痴漢事件で弁護士が行う弁護活動
⑴ 被疑者の早期釈放
痴漢の被疑者は、犯行現場で被害者や目撃者等の第三者、通報を受けて駆け付けた警察官に現行犯逮捕される可能性があります。
逮捕された場合、逮捕から48時間以内に検察官に身柄が送られます。
検察官が勾留の必要性ありと判断した場合、裁判官に勾留請求をします。
これが認められると、被疑者は10日間から20日間におよぶ身体拘束をされます。
勾留された場合に被疑者本人に及ぶ不利益は計り知れません。
そのため、依頼を受けた弁護士は、被疑者の早期釈放を目指して活動します。
まずは、被害者が拘束されている警察署の留置場に駆けつけ、被疑者と接見をします。
初回の接見では、事件の詳細と被疑者の社会的な立場、家族関係、犯行が事実か否か、自白しているか否かなどを聞きとった上、弁護方針を立てます。
そして、今後の捜査手続きと起訴不起訴の処分の見通しや、取り調べを受けるにあたって注意するべき点などをアドバイスします。
犯行が事実であり、素直に自白済みであれば、例えば被疑者に反省文を書かせ、家族に身柄引受書を作成してもらい、「証拠隠滅や逃亡のおそれはないから勾留の必要性がない」との弁護士の意見書とともに検察官に提出します。
検察官と直接に面談して意見を伝えることもあります。
検察官が弁護士の意見を受け入れず勾留請求をしたときは、裁判官に対し、請求を却下するよう意見書を提出したり、直接に裁判官と面談して意見を伝えたりします。
それでも勾留決定が出された場合、準抗告という不服申立てを行い、裁判官の行った勾留決定の取消しを求めます。
⑵ 被害者との示談交渉
弁護士は、被疑者の早期釈放のために、以上の活動だけでなく、被害者との示談交渉にも着手します。
示談は、被疑者が示談金を支払う代わりに、被害者が犯行を許し、当事者間では事件は解決したことにするという内容の合意です。
被害者との示談が成立すれば、以降の刑事手続きにおいて有利な事情として扱われます。
すなわち、検察官は被疑者を起訴するか否かの判断に当たっては、犯行の重大性、反省しているか、前科の有無、被害者の処罰感情等を総合考慮するのですが、示談の成立は被疑者に有利な証拠なので、不起訴処分となる公算が高まるのです。
痴漢事件の示談は弁護士に依頼すべきと言うのは、当事者同士だと示談交渉が困難だからです。
それは以下の事情によります。
・被疑者が身体拘束されている場合、自ら被害者のもとに出向くことができず、示談交渉ができない。
・被疑者本人は、被害者の連絡先を知らないのが通常で、また、被害者も痴漢の犯人に連絡先を教えたがるわけもなく、結局示談交渉ができない。
・示談をするためには法的知識や経験が必要で、法律に詳しくない方が示談を行うと、適切な合意内容の示談が成立しない。
示談が成立した場合、示談書にその旨を記し、被害者に示談金を支払います。
そして、示談書を検察官に提出します。
起訴を阻止するために示談は、検察官が起訴処分をする前にしなければなりません。
起訴不起訴の処分は、逮捕から23日以内に決められますから、示談交渉にはスピードが必要です。
そのため、早期に弁護士に依頼し、事件に対応してもらう必要があります。
3 弁護士費用相場
弁護士に依頼するとしても、問題となるのは弁護士費用です。
弁護士費用は法律事務所ごとに異なるので、依頼しようと考えている法律事務所のホームページで確認するなどしましょう。
ここでは、弁護費用の内訳を相場とともに説明します。
⑴ 相談料
弁護士に法律相談する際に、相談料がかかる場合があります。
相場は1時間5000円〜1万円です。
もっとも、現在では初めての相談の場合は所定の時間分を無料としたり、電話・LINE相談等のサービスを実施したりしている事務所もあり、以前と比べて法律事務所に相談しやすくなっています。
⑵ 着手金
弁護士に弁護活動を依頼する際、事件に着手することでかかる費用です。
事務所によっては、起訴前弁護と、起訴後弁護を分けているところもあります。
着手金相場は、10万円~40万円程度です。
⑶ 接見費用(接見日当)
逮捕・勾留している被疑者と接見する際にかかる費用です。
着手金に含めている事務所もありますが、これを必要とする事務所では、接見は一日ごとに2万円程度が相場です。
⑷ 公判日当
公判期日に裁判所へ出頭する際にかかる費用です。
これも着手金に含めている事務所もありますが、これを必要とする事務所では、一日ごとに2万円程度が相場です。
なお、着手金とは別に接見日当や公判日当を必要とする事務所では、着手金をリーズナブルな金額に設定し、実際に接見や公判のために弁護士が活動した回数に応じて金額を加算しているので、依頼者からすれば、無駄な費用を抑えることができるメリットがあります。
⑸ 成功報酬
弁護活動の結果(早期釈放、不起訴処分、執行猶予付き判決、無罪判決等)にかかる費用です。
相場は30万円~40万円程度ですが、事件によっては高額となる場合もあります(痴漢冤罪を主張する等)。
⑹ 日当・実費
日当は、地方出張など弁護活動で弁護士が長時間拘束された場合に発生する費用で、半日3万円~5万円程度です。
実費は交通費・コピー代等弁護活動を行うのにかかった経費です。
痴漢事件で否認事件でない場合は、通常、1~2万円です。
なお、弁護士費用に加えて被害者との示談金も支払わなければなりません。
痴漢の示談金相場は30万円程度ですが、当事者間の合意で決まるという性質上、これ以上の金額になる場合もあります。
そのため、痴漢事件においては、示談金と弁護士費用合わせて最低でも総額100万円程度必要となると考えておきましょう。
痴漢で逮捕された場合の示談交渉は弁護士へ依頼 不同意わいせつで示談するためには弁護士へご相談を